DIサミット2025セッションレポート「右脳×左脳×異能による共創型データプラットフォーム事業とは」
- TAG : Data-Informed | DIサミット | データインフォームド | 講演・発信
- POSTED : 2025.08.20 11:30
f t p h l
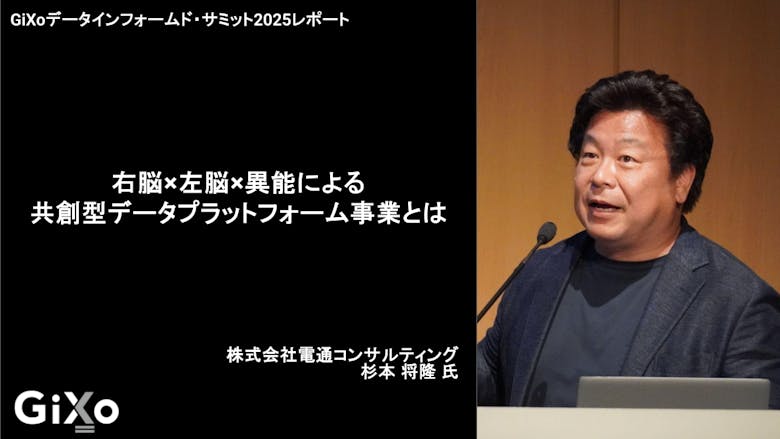
2025年4月22日に当社が主催した「GiXoデータインフォームド・サミット2025」の講演「右脳×左脳×異能による共創型データプラットフォーム事業とは」のセッションレポートをお届けします。
登壇者紹介
| 株式会社電通コンサルティング 専務執行役員/シニアパートナー 杉本 将隆 氏 |
本レポートでは、講演の内容を一部抜粋してご紹介します。
自己紹介とこれまでのキャリア
私は宮崎県出身で、大学時代はギックスの網野さんと同窓・同年代です。鉄道会社で地域通貨事業を立ち上げていた2009年当時、セミナーをきっかけにアクセンチュアに勤めていた網野さんを訪ねて、私たちは出会いました。
その後コンサルティング業界に転じ、約16年になります。直近では、ホールディングス体制に移行してビジネスコンサルティング領域を強化する予定であった電通グループ(電通コンサルティング)に参画しました。
私はプロフィールに「イントレプレナー(社内起業家)」と記している通り、鉄道会社では約10年間、新規事業や地域通貨事業の立ち上げに取り組むほか、事業創造コンサルタントとしても16年ほど活動してきました。また、アントレプレナーシップ(起業家精神)教育家として大学で教鞭もとっていまして、「地域づくり」「事業づくり」「人づくり」を自分のライフワークとしています。
| 株式会社電通コンサルティング 専務執行役員/シニアパートナー 杉本 将隆 氏 シリアルイントレプレナー&事業創造コンサルタント&アントレプレナーシップ教育家の3つの顔を持つ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、大手鉄道会社に就職。地域通貨等複数の新規事業立ち上げを経験。九州大学ビジネススクール在学中に、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に移り、B2C向け新規事業・CRM戦略チームを6年間リード。PwCコンサルティング合同会社では、地方創生チームと地区事務所を立ち上げ統括責任者。2019年9月より現職。九州大学QREC客員教授、亜細亜大学ビジネススクール講師。中小企業診断士、1級FP技能士、経営学修士。 |
共創型データプラットフォームを支える4つの技術進化
まずは「共創型データプラットフォーム」の事業を語る上で外せない技術の進化について、4点お伝えいたします。
1.IoTデバイスによるデータ取得範囲の飛躍的な拡大
2010年代以降、IoT機器の普及とともに、世の中に流通するデータが加速度的に増加しています。iPhoneひとつとっても様々なセンサーが搭載されており、これまで取得が難しかった多様なデータの収集が可能になりました。
2.通信技術によるデータ流通量の増加
iモードの時代から現在の5Gに至るまでの30年間で、最大通信速度は約100万倍に増加しました。その一方で通信料金は劇的に安くなり、低コストで大量のデータを取得・活用できるようになっています。
こうした進化によって、例えばお天気情報アプリのように、リアルタイムかつ高精度なビッグデータの活用が可能になりました。
3.AI技術による個人単位での最適化
AI技術の加速度的な向上により、これまで顧客セグメント別であったマーケティングが、パーソナルデータ起点で自動最適化できるようになりました。例えばロレアルの「Beauty Genius」というサービスは、生成AIによって、ユーザーの肌の写真などの情報をもとに個別に診断を行い、スキンケアやメイクアップのアドバイスを提供します。さらに、最適な製品のリコメンドや、バーチャルでの試用体験も可能にしています。
4.CX(カスタマーエクスペリエンス)技術の進化
例えばアリババグループのECサイト「Taobao」のアプリでは、ユーザーの年齢層に応じてフォントサイズやレイアウト、レコメンド商品といったUIが自動的に切り替わります。つまりこれまで画一的だった顧客体験の個別最適化が可能になっているのです。
これまでは、技術やコストの制約から「顧客に広くリーチすること(Reach)」と「提案品質・顧客体験の質(Richness)」を両立するのは困難でした。
しかし技術の進化によってこのトレードオフが打破され、両立が可能になったのです。
共創型データプラットフォームの全体像と価値創出のポイント
ここからは、「共創型データプラットフォームとは何か」についてお話しします。
従来は官民問わず、各組織がそれぞれ顧客や住民に対してサービスを提供してきました。この従来モデルでは、組織ごとに規約同意を取ってサービスを運営するため、システムやマーケティングへのコストがそれぞれの組織で発生します。さらにレガシーなオンプレミス型のシステムを使っていたり、デジタルマーケティングが上手くいっていなかったり、という個別の課題から、組織単位でコストと効果のバランスを取るのが難しい状況でした。
これに対して「共創型データプラットフォーム」では、複数の事業者が業務資本提携を通じて新たな運営主体を作り、連携してサービス提供するモデルです。各事業者が持つ資産や影響力を組み合わせることで、顧客データを連携し、シームレスな顧客体験を提供します。複数の事業体が一体となってサービスを提供できる点が、大きな特長です。技術の進化により、このモデルが実現可能な時代になっているのです。
「共創型データプラットフォーム」の代表的な事例としては、次の3つが挙げられます。
- PayPay(日本):決済サービス起点
決済業界のスタンダードをディスラプト(破壊)。手数料ゼロで中小加盟店を拡大。ユーザーに破格の還元を実施。経済圏を形成しながら、圧倒的なシェアを獲得。 - Grab(東南アジア):配車サービス起点
配車サービスからデリバリーや金融サービスなどに事業を多角化。マーケットプレイス開放やM&Aを通じて共創型にシフト。 - WeChat(中国):コミュニケーション起点
チャットアプリの中に独自のミニアプリを組み込み、行政手続きや各種決済がアプリ1つで完結できる仕組みを実現。
これら3つの事例のように、「共創型データプラットフォーム」は、絶え間ない顧客理解と価値創造のサイクルによって、収益化が可能なのです。
そのサイクルを事業収益化に結実させるポイントは3つあります。
1.事業価値向上
よくある「各社で連携して何か一緒にやりましょう」という取り組みは、キャンペーンや実証実験(PoC)で終わりがちです。それでは持続可能な事業にはなりません。地域創生の取り組みでもこのような事例は多くみられます。
立ち上げの段階から、事業のパーパス(目的)・事業モデル・共同事業体の3つを揃え、事業価値を高めることが重要です。
2.顧客価値向上
共同事業体があることで、参加事業者はお互いの利害対立を超え、仲間として地域活性化やウェルビーイング社会の実現といった共通の目標に向き合えます。その結果、未来を見据えた新たな顧客サービスが創出されるのです。
さらに冒頭お伝えした4つの技術進化によって、コストと提供価値のトレードオフを突破できる時代になったからこそ、データ起点で顧客体験の高度化が可能になり、新たな価値創出につながります。
3.投資コスト低減
共同事業体による共用化によって各社の投資やマーケティングコストを抑えつつ、Reach(提供範囲)とRichness(体験の質)を段階的に高めていくのです。
大切なのは、アジャイル型で小さな失敗を繰り返しながら、ステップを踏んで改善し、成功率を上げつつ拡張していくことです。
この3つのサイクルを動かすために、初期のビジネスプランが極めて重要です。同時に、顧客の反応やステークホルダーの変化に応じてビジネスプランに修正をかけていく“しなやかさ”も重要となります。
「ふくいのデジタル」が示す共創の可能性
「共創型データプラットフォーム」は大きく分けて、「官主導」「民主導」「官民連携」の3類型がありますが、今回は事業性と社会性の両立という観点から、「官民連携」の取り組みを紹介いたします。
地方創生で用いられる連携概念に「産官学」がありますが、近年はこれに金融機関やメディア・マスコミを加えて「産官学金言」とも言います。
この連携体制を先駆的に実現しているのが「株式会社ふくいのデジタル」です。これは福井銀行と福井新聞社の共同出資により設立された会社で、「福井に暮らす人、福井を訪れた人のウェルビーイングを高めていく」というパーパスを掲げる、民間企業でありながら半ば公共的な性質を持つ存在です。
同社が提供する「ふくアプリ」は、福井県内の全自治体の施策——給付金や地域通貨、健康、子育て支援など——を集約した統合サービスです。行政施策に加え、民間サービスの連携・提供も進んでいます。地域通貨事業は収益化の難易度が高いのですが、この事業は設立2年目から単年度黒字化を達成しています。
では次に、これらの官民連携事例に対して、よくいただく3つの疑問にお答えします。
1.ただの行政案内アプリは日常的に使われないのでは?
確かに、行政系アプリは縦割りや単年度主義の影響で、住民に利用されずに終わるケースも多いです。
ふくアプリでは「三方良し」の視点を重視し、「生活者・加盟店」「プラットフォーム運営事業者」「自治体」それぞれにメリットがある設計にしています。
生活者にとっては、複数のアプリを使い分ける必要がなく、1つのアプリで行政と民間サービスの両方が受けられる利便性が魅力です。また、加盟店にとっては、紙や電子が混在する煩雑な運用から解放され、地域施策への参画・協力が集約化されてスムーズになります。
プラットフォーム運営者にとっても、統合IDによるデータ一元化で域内データを把握しやすくなり、新しい政策やサービス開発につなげることが可能です。
そして行政も、プラットフォームを活用した施策のデジタル化やコスト削減が期待できるのです。
2. 収益性が難しいのでは?
大胆でユニークな事業構想と、段階的な事業プランを組み合わせることで、リスクを低減しながら収益性を確保しています。事業パーパスを定め、必要な機能を明確にし、3階建ての事業ポートフォリオを構築し、半公共的な事業主体が運営することで、持続可能な仕組みを実現しています。
3. 資本力のあるメガプラットフォーマーに負けるのでは?
地域に根差す地方銀行、新聞社、交通事業者など、地場のプレーヤーが持つ影響力と信用力を結集した座組とビジネスモデルにより、メガプラットフォーマーにはない地元密着の強みを発揮し、持続可能な事業運営を行っています。こうした取り組みは、我々が構想から計画策定、事業体組成、定着化まで一気通貫で支援しており、全国各地で広がりを見せています。
本日の話を纏めますと「共創型データプラットフォーム」を成功させるには次の3つが重要です。
- 夢やロマンを描く(右脳)
- データ起点で確からしいプランを段階的に動かす(左脳)
- 産学官勤労言の異業種プレーヤーをまとめて新たな価値をつくる(異能)
皆様にとってこれからのビジネス拡張のヒントになれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。
f t p h l