DIサミット2025セッションレポート「システムモダナイゼーションに実際に取り組んでの裏話」
- TAG : ADS | CU/ADS | Data-Informed | DIサミット | ギックス顧客事例 | データインフォームド
- POSTED : 2025.05.15 09:30
f t p h l
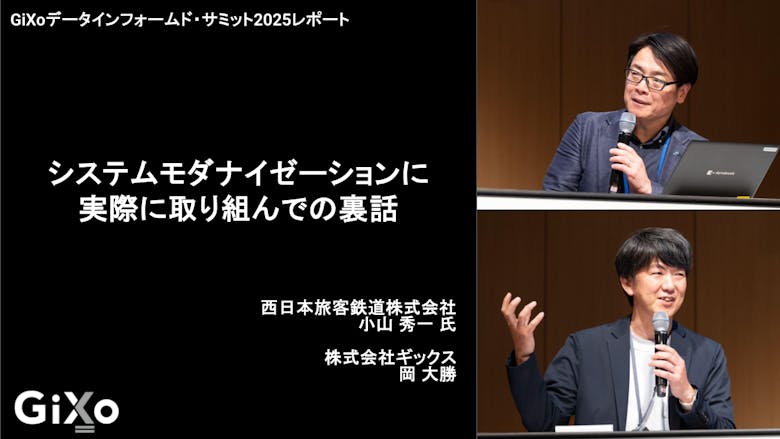
2025年4月22日に当社が主催した「GiXoデータインフォームド・サミット2025」のパネルディスカッション「システムモダナイゼーションに実際に取り組んでの裏話」のセッションレポートをお届けします。
登壇者紹介
| 西日本旅客鉄道株式会社 デジタルソリューション本部 システムマネジメント部 担当部長 兼 WESTERモール推進室長 小山 秀一 氏 1996年JR西日本に入社。駅員、乗務員、ダイヤ作成部門、営業部門を経て2001年10月に総合企画本部IT推進室に着任。 主に顧客向けシステム(ネット予約、会員管理、コールセンターシステム等)を担当。2021年4月より、DX組織において、JR西日本グループのデジタル戦略において必要なデータ利活用のための基盤整備、内製開発、モダナイゼーション、ネットワークインフラ刷新等を推進中。直近は新たな決済サービス「Wesmo!」の開発にも参画。 株式会社ギックス上級執行役員/Chief Technologist & Chief Architect 岡 大勝 日本DEC、日本HP、日本ラショナルソフトウェアにてアーキテクチャ設計および開発プロセス改善を専門に活動。2003年に独立し、先端技術によるエンタープライズITの最適化に取り組む。2019年にZOZOに参画しZOZOTOWNの全面リプレイスの設計責任者を務める。2022年5月に株式会社ギックスに入社。技術責任者を務めるとともに、顧客企業のシステムと組織のモダナイズを推進している。2013年に日経BP社「日本を代表する18人のITアーキテクト」の一人として選出。NoOps Japan Community発起人。 |
本レポートでは、パネルディスカッションの内容を一部抜粋してご紹介します。
システムモダナイゼーションの2つのメリット
小山:我々のシステムモダナイゼーションについては、まず岡さんに伴走いただいた「ICOCAポイント管理システム」の案件が取っ掛かりだったんですけれども。
その際、先ほどの講演(※JR西日本におけるシステムモダナイゼーションの取り組み)でも触れました「社内から“理念はわかるけれども現実は…”という喧々諤々があった」という内容について、少し紹介してもよろしいでしょうか。
岡:はい、お願いいたします。
小山:これはよくある話だと思いますが、「モダナイゼーション」という掛け声は色々なところで華々しくかかっているんですが、いざ現実として事業会社の中で「システムモダナイゼーションをしましょう」という話が出ても、そもそも業務システムを使っているユーザーサイドから「使い慣れたものを別にそんな無理して変えなくていいよ」という意見が出てきます。
そのため社内で「システムモダナイゼーションはユーザーのためにやるんだ」ということを訴えても、システムを担当しているメンバーから「いや、ユーザーが今のままでいいと言っているのに、何故そんなことをシステム部門から主張していかないといけないんですか?」と、そういった生々しい声が多数出るわけです。
こういった声に対して、当時岡さんからいろいろとご指導いただいた内容をご紹介お願いできますでしょうか。
岡:はい。これは本当によくある話ですね。「モダナイズ」とは、基本的な機能は変わらずシステムの裏側を刷新する、という話で語られることが多いですし、まさにその通りでもあるのですが、ではユーザーさんへの直接の価値って何でしょうか、という話ですね。
基本、エンタープライズシステムのユーザーさんは、UIがどんなに使いやすくかっこよくなっても、元のシステムの方がいいんです。
個人的に使うスマホアプリだったら、使い勝手が良くなっていった方が嬉しいんですけれど。業務で使うシステムは、業務マニュアルを変えなければいけないとか、教育をやり直さなければいけないとかで、ちょこちょこ変わってしまうと困るというユーザーさんが多分99.何パーセント…ほぼ全てのユーザーさんが、そんなことは望んでいません。
ではどのようなアプローチが必要かと言いますと、先ほどの小山さんのセッションでもありましたが、モダナイズのメリットは「変化への適応力を高めること」と「コスト競争力を高めること」、この2点に尽きます。
なので、前提として変化が必要ないシステムは、現場としてもシステム部門としてもモダナイズの必要性がないんです。
ちなみに、クラウドリフト、つまりクラウドに載せ替えるだけではモダナイズではありません。クラウドにただ載せるだけですとコストが上がりますので。やはり「変化への適応力を高めること」と「コスト競争力が高まること」が実現されてこその、モダナイズです。
では組織全体で考えてみましょう。
色んなシステムが今のままでいい、という状態が続いたとしても、ハードウェアやOSの更改は5年とか数年ごととかにやってくるわけなんですよ。それを何回か繰り返すと、例えば10年後、15年後には、ソフトウェアやアプリケーションは同じで、下回りだけ新しくなっている状態になります。これが組織として健全かどうか考えると、やっぱり不健全なんです。
いちばん大切な業務知識やドメイン知識を、もはやシステム部門の中で誰も持ってないままに、インフラの更改だけをしている。そんな中で、業務の変化・市場の変化があっても適応できるかというと、全く話にならない。では、イチから要件定義をして、今の新しいニーズに合わせて、新しいUIで、3年がかりや5年がかりでシステムを作りましょう…という話にしかならないんですよね。
クラウド技術が我々にもたらすものとは
岡: 先ほどの小山さんの講演でも「組織的に2006年~2007年あたりからガラッと、特にシステムを取り巻く環境が変わりました」ということを「クラウドネイティブ」というキーワードでお話されていましたが、ここで「Cloud Native Definition」をご紹介します。
これはいわゆる「クラウドネイティブ技術」の定義で、色々なことが書いてあるんですが、「スケーラブルなアプリケーションを実行するための能力を組織にもたらします」とか…少し抽象的な言い回しで分かりづらいんですが、結局は「軽量で、分離・分散で、疎結合で、宣言的な作りをしているクラウドネイティブ技術を使うことで実現できること」が書いてあるんです。世の中では、AWSやAzureやGoogle Cloudといったクラウドサービスの使い方についてはいろいろ語られていますが、そもそもクラウドネイティブ技術が何をもたらしてくれるのか、というところを誰も言ってないんですよね。
では実際にクラウドネイティブ技術によってユーザーがどんなメリットを得られるのか、ということを少し意訳したものがこちらです。
スケーラブルなアプリケーションをモダンで動的な環境、つまりクラウドプラットフォームに乗せることで、疎結合なシステムができる。さらにそれを自動化と組み合わせることで、影響の大きな変更も、最小限の労力で頻繁かつ予測通りに行うことができる。
つまり、結構クリティカルなリリースも、予測通り、自動的に、影響最小限の影響で、無停止で行うことができるようになります。うまく、ちゃんと使えば、ですが。
これを「ちゃんと使えてない」ことがすごく問題なんですが、ちゃんと使うことで、先ほどお話しした、組織にある色々なシステムを停止させず継続的に、進化させていくことができる、継続的に変化に適応し続ける、かつコストをどんどん下げていける…そういうことを実現できる技術なんです。こういった技術を何の説明もなく我々は提供されて、これまでのレガシー技術と同じように使ってしまっている現場があまりにも多いんです。なので「ちゃんと使いこなしたい」んですよね。
そのあたりを小山さんをはじめ、JR西日本のシステム部門の皆さんに、勉強会という形でご説明させていただきました。
小山:はい。当初我々は「モダナイゼーション」というのは、世の中がその方向に舵をきって、トレンドとしてシフトしてるんだから、十把一絡げにやるべきじゃないのか、みたいな頭にどうしてもなってしまっていましたね。そんな時代に取り残されないために、と言っていながら、そもそもの本質と言いますか、何故モダナイゼーションをしなければいけないか、ということが頭の中で整理できておらず、腹落ちしていなかったんですよ。
その結果、「パブリッククラウドにリフト・シフトしたいんです、でも要件としては基本無停止で、データベースもガチガチなものとか、今使っているソフトウェアをそのまま移植するとか、基本的にはあまり中の作りも変えたくない…」という、リスクを全く取りたくないけれどもモダナイゼーションしたら何か恩恵があるんじゃないか、という考えで、組織と人のマインドセットは全然変わっていませんでしたし、その点が本質的な問題でした。
岡さんからは「いきなり全部に手を広げてやるっていうのは、そもそも進め方としてはよろしくないから、まず一つやってみて、それがもたらす価値って何なのか、ということを一度しっかり自分たちで理解をして実践して、そして広げていこう」という、ご支援をいただいたかなと思っています。
そのまず一つ目、初手として実践したのが、先ほどの講演でご紹介したICOCAポイント管理システムの案件です。本当に勉強になりました。
システム運用の構造から見直す“NoOps(ノーオプス)”という概念
岡:そうですね。私からICOCAポイント管理システムをざっくり説明しますと、巨大なバッチ処理が夜な夜な動いていて、利用条件からポイントを算出して、それをポイント台帳システムに渡してあげる…というものなんですが、この巨大なバッチ処理がものすごい密結合で作られていたんです。
皆さんお分かりだと思いますが、すごく複雑なジョブネットで組まれているので、それをいかに分離させるか、という取り組みであったり、巨大なデータ×巨大なデータの計算の結合度の分離や実行させるクラウドの分離、といった複数のアプローチを使って疎結合化することで、それぞれの処理を分散処理しやすいサイズにコンパクト化しました。
そして、バッチがこけた時にも単純なリトライでバッチを流し直せるように冪等性(べきとうせい:ある操作を何度繰り返しても結果が同じになるという性質)をちゃんと担保する。できるだけ手を入れやすく、運用を軽くしていこう、ということで、結果、システムコストも運用コストも下がり、そしてシステムを変化させるアジリティを高めることができるようになりました。
そのベースになっている概念が、「NoOps(ノーオプス):No Uncomfortable Ops」という、要は「システムの嬉しくない運用をなくしていこう」という考え方です。
私が前職時代、アメリカのあるクラウドベンダーを訪問した際、コンテナ技術のプロダクトマネージャーの方がこう仰っていました。
「我々がこのコンテナ技術にコミットして頑張っている理由は、コストを下げたり、運用をしやすくしたりすることで、結果的にユーザーの利便性が高まるからだ。ここを目指して、我々は開発している。特にコスト面では乾いた雑巾を絞りに絞ってコストを下げていく、そのためのコンテナ技術なんだ」と。このお話を伺ったことをきっかけに、私がいろいろなところでお話させていただいているのが「NoOps」というアプローチです。
システム運用や保守の面において、バックエンドシステムが疎結合になって何が嬉しいかというと、ここまでお話ししてきた運用保守コスト(人的コスト・システムコスト)の最適化・最小化や、実際のシステム運用・保守現場で必要な監視負担の軽減があります。
例えば100万件のバッチ処理を実行していて、99万件目で失敗したら、これまでの現場であれば、続きから処理をするのか、頭から処理を流し直すか、というところを考えることから始めることが多いと思います。それを、単純なリトライで復旧することができるようにすることで現場の負担を減らしたり、さらには監視そのものを不要にできるようにしたい。このアプローチを各システムに広げていくことで、現場の負担、具体的には夜間停止してメンテナンスします、とか連休中にシステム部門の人は総出でシステムをメンテナンスします、という負担の軽減に繋がります。
冒頭お話しした Cloud Native Definitionで示されている世界が実現できれば、システム運用・開発現場の働き方改革になるんです。システム運用部門の方も普通に9時-5時で働けていて、システムは基本的に自律運用されている。障害があっても自律的に回復して、その報告だけあがってくる、そういう世界が実現できますし、実際クラウドベンダーの裏側はみんなそうやってるんですね。
そういったことはエンタープライズシステムで十分できるんです。クラウドベンダーの裏側は一般企業よりももっとミッションクリティカルなんですよね。何千何万のお客様がいて、一分一秒がお金に換算される世界なので。なので「ミッションクリティカルシステムだから今までと同じロバストネス(堅牢性)重視の設計をしなければいけない」っていうのはもう時代遅れなんです。
「サーバーを止めない」という考え方は捨てて、「いつどこのサーバーが障害で止まっても、次の瞬間には別のサーバーでシステムインスタンスが起動していて、データは一貫性も保たれています」というレジリエンス(回復力)のある設計をしてあげることで、このNoOpsは実現できますし、それを実現しているのがICOCAポイント管理システムになります。…ですよね小山さん?(笑)
小山:はい(笑)ただ、最初はそのあたりがその運用するメンバーには伝わらなくて。恥ずかしながら、これは我々の責任転嫁とも言えるかもしれませんが…もともと当社の中の情報会社などが採択したベンダーさんにシステムを作ってもらっていましたので、システムに何かあったら我々としても初動は取らないといけないですけど、実際に直すのはベンダーさんなので、そのベンダーさんに対応してもらうということで、運用・保守における直接的な責めをある意味免れている部分はありました。
ですが、これを「モダナイゼーションをして自分たちの手で」などと言い始めると、結果、そのシステムをお世話するベンダーさんの責務が自分のところに降りかかってくると思い込んでいて、それはむしろ自分たちの首を絞めるからやりたくない、という考えになりかけていました。
ですが「NoOps」という概念はそうではない、と。夜間に情報が止まってしまって駆けつけるとか、そういう構造をそもそもから改めませんか、それは実は今適用できる技術で実現できるんですよ、ということを運用メンバーに共有しました。
そこがまず発想転換の契機となり、結果としてICOCAポイント管理システムは運用メンバーからも非常に喜ばれています。
岡:私自身も発想を完全に転換するまで5、6年かかりましたので全然大丈夫です(笑)
小山:システムの運用は運用ですごく大事なのですが、その大事な役割を担う運用メンバーの仕事のやり方を、今まで通りでというよりも、さらに高度化する…例えば運用の高度化とか、サービスをどうやってコントロールしてお客様に不便を与えないかという、彼らがより活躍できるようなことに目を向けさせたかったんです。作業立ち会いみたいな仕事ばかりに忙殺されないようにしたい、夜討ち朝駆けのような仕事を脱却したい…これが取っ掛かりとなって、今は徐々にこれまで以上のことに自分たちもチャレンジしたいという人が増えてきてるかなと思います。
変化に対する“勢”を身につける
岡:このように「ユーザーさんは変化を望まない」という前提がありつつ、では我々システムサイドとしては何をどう変化させていくのかを、NoOpsの概念のもとで大きくメリットとして出していけば「こんなにコストが下がって、こんなに運用・システム部門の負荷が減るんだったら、じゃあやろうよ」という話になることが多いと思うんですよ。
そしてその際に、やはり一番転換しなければいけないのが「勢(せい)」についてです。
これは孫子の勢篇で語られている「勢」のことで、適材を適所に配置して、あとは自ずと彼らに任せれば、闘いは勝つべくして勝つ、という考えです。
適材を適所に配置することによって生まれるこの「勢」というもの、組織の「勢」、チームの「勢」は、見えないんですけど、存在してるんですよね。売上が右肩上がりの営業チームとか、どんなトラブルが発生しても的確で適切な対処ですぐに復旧させる運用チームとか、皆さんの周りにもあると思うんですが、それはそのチームが活動の中で「勢」を活かせている状態だと言えます。こういう事態だったら自分はこれをやる、私はこれをやる、リーダーは適切にアナウンスして外部と調整する、みたいなことが個人個人が自律的に自然にできていてチームとして調和して動けている。システムをモダナイゼーションする際に、合わせて組織行動もモダナイゼーションしなければならない。その際にこの「勢」というものを生かすという発想が重要になります。
変化しないのであれば、同じことを繰り返すことで「勢」は自ずと高まっていきます。しかし今の時代、世界は日々変化が激しくなっています。ビジネスではAIやEVの台頭、市場環境でもトランプ大統領から不確実で巨大な変化が投入されています。このような時代では ”変化に適応するための「勢」” を身につけることで、変化するのが当たり前ですよ、というマインドを組織が持つことが必要になります。
例えば、「新しいサービスが出てきたから、それをシステムに織り込んですぐリリースしよう!」「一週間後にできるか?」「はい、できます!」と言えるぐらいの変化への「勢」を身につけていくことです。
そして、もう一つ大切なのは、その「勢」を殺さないことです。
実はシステム業界って「勢」を簡単に殺しちゃうんですね。新しいシステム構築をベンダーさんにお願いして、ベンダーさんがガーッと「勢」を発揮して開発しシステムをリリースしました!…となった後に、開発チームが全員解散して運用チームに引き継ぐんです。そうすると「勢」がゼロになる。せっかく高まった「勢」をすぐ殺しちゃうんです。
そこを、ちゃんと「勢」を生かして変化に適応し続けるようにしていきたいんですよ。これが組織的にできれば、個別システムでモダナイズが必要なのか?というところへの回答にもなると思うんですね。組織として変化することに慣れていれば、式年遷宮じゃないですが、次に着任する人も同じ「勢」を身につけて、人が抜けても入れ替わっても組織としての「勢」は変わらない。見えないけれどそれがすごく大事なところなんです。
OODAやSECIモデルによって部分的には可視化されてるんですが、これらを組み合わせて考えると、やっぱり「勢」をいかに生み出し維持するか、そこに尽きるんです。PDCAよりOODA、形式知も大切だけど暗黙知ももっと大切にしようよ、というところにも繋がりますね。
このような観点についてもJR西日本さんにはお話しさせていただいて、システムだけをモダンにしても、それをウォーターフォールでクローズドエンドで作ったら「勢」なんか生まれっこない、「勢」はゼロにリセットされてしまいます。継続的に「勢」を生かすために、このあたりは(NoOpsの概念と)両輪ですよ、という話をさせていただいてます。
小山:ありがとうございます。今回ICOCAポイント管理システムのプロジェクトに携わったメンバーが、変化対応力を今回身につけて、「勢」がそこに生まれています。これからはそのチームが自分の分身を作って行き、組織の色々なところに拡散していって、それぞれのチームがそれぞれの取り組みの中でこの「勢」を止めないようにしていこう、という流れが出てきつつあるように感じます。
最初は地道な取り組みだな…と思ったんですが、徐々に徐々にそれが渦となって大きくなってることに対しては自信を深めているところです。今後も引き続き我々としてはチャレンジを、このスライドにある三つ(勢、変化、練度)をしっかり意識して取り組んでいきたいと思っております。
岡:ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
小山:今回の内容に付随した資料もまだいっぱいあるんですけれど…岡さんと我々が本当に一緒に取り組んだ血と汗と涙の結晶なんですが、お時間が来ましたので、今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
(参考記事)
・【前編】レガシー脱却から始まる、組織の意識改革と技術進化 JR西日本「ICOCAポイント管理システム」刷新がもたらした適応力の文化(2025/05/08)https://www.gixo.jp/blog/27306/
・【後編】“顧客理解”を起点に、心地よい提案を届ける JR西日本 小山秀一氏が語る「CU/ADS」で叶えたデジタル時代の“おもてなし”体験 (2025/05/08)https://www.gixo.jp/blog/27315/
f t p h l