DIサミット2025セッションレポート「JR西日本におけるシステムモダナイゼーションの取り組み」
- TAG : CU/ADS | Data-Informed | DIサミット | ギックス顧客事例 | データインフォームド
- POSTED : 2025.06.13 16:00
f t p h l
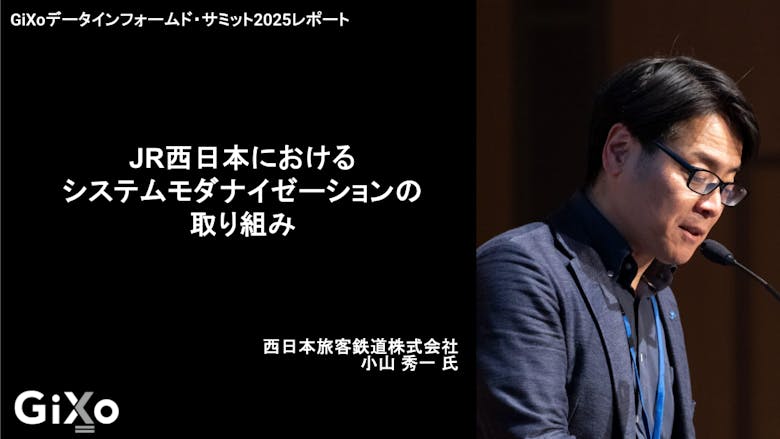
2025年4月22日に当社が主催した「GiXoデータインフォームド・サミット2025」の講演「JR西日本におけるシステムモダナイゼーションの取り組み」のセッションレポートをお届けします。
登壇者紹介
| 西日本旅客鉄道株式会社 デジタルソリューション本部 システムマネジメント部 担当部長 小山 秀一 氏 1996年JR西日本に入社。駅員、乗務員、ダイヤ作成部門、営業部門を経て2001年10月に総合企画本部IT推進室に着任。 主に顧客向けシステム(ネット予約、会員管理、コールセンターシステム等)を担当。2021年4月より、DX組織において、JR西日本グループのデジタル戦略において必要なデータ利活用のための基盤整備、内製開発、モダナイゼーション、ネットワークインフラ刷新等を推進中。直近は新たな決済サービス「Wesmo!」の開発にも参画。 |
本レポートでは、講演の内容を一部抜粋してご紹介します。
JR西日本の再構築戦略とシステム部門の方針
JR西日本グループはコロナ禍で大きなダメージを受けたことをきっかけとして、立ち直りを図る上で、「鉄道システム」「顧客体験」「従業員体験」の「3つの再構築」という方針を掲げました。
これらを実行していく上で、すべてにおいてテクノロジーとデータの活用を軸とすることを、戦略として打ち出しました。
その戦略の実現において、システム部門として掲げた方針が、以下の三層構造です。
一番下のレイヤ1(ピンク色部分)は土台として、人財や技術などの組織能力を提供すること、続くレイヤ2(緑色部分)では、インフラやセキュリティといった基盤を確立すること、そして一番上のレイヤ3(黄色部分)では、変化するニーズに柔軟に対応できるシステムを提供すること、という構造です。
このレイヤ3には、本セッションのテーマでもある「モダナイズ」を明記し、システム部門のミッションとしました。
その上で、「モダナイズ」が我々にもたらすメリットについても定義を行いました。
これまでの密結合なシステム構成を改め、機能ごとに再利用性を確保する「疎結合アーキテクチャ」を採用することで、システム改修や障害時の影響軽減や、運用自動化による負荷削減を図ります。また、これまで外注していた開発体制の内製化にもチャレンジし、納期・品質・コストの観点から価値を生み出そうと考えました。
しかし、そのような方針を掲げてはみたものの、現場レベルでは全く機能せず「理念は理解できるが、実際にどう進めていけばよいのか」という葛藤の声があちこちから噴出しました。耳の痛い指摘も多く、思うように進まないことへのもどかしさを感じる日々が続きました。このあたりの詳細については後ほど、ギックスの岡さんとのパネルディスカッションでご紹介したいと思います。
ICOCAポイント管理システムの刷新が転機に
そのような状況の中、当社の交通系ICカード「ICOCA」の利用に対してポイントを付与するシステムを刷新したいという案件が、我々の元へ舞い込んできました。
まず、「ICOCAポイント」について簡単にご説明します。
従来は紙の割引切符を販売しており、例えば同一区間を10回分の価格で11回利用できる回数券や、通勤・通学のピーク時間外に移動需要を喚起するための「昼間特割きっぷ」などの商品がありました。
しかし、紙の切符は金券ショップに持ち込まれ、バラ売りされてしまうという課題が長年指摘されていました。
そこで、ICOCAの乗車履歴に応じてポイントを還元する方式へと転換しよう、ということで構築したのが「ICOCAポイント管理システム」であり、2018年にサービスを開始しました。
このシステムは、鉄道・交通利用にとどまらず、物販などの購買でもポイントが貯まるサービスとして構築しました。
しかし初期構築の段階では、限られた時間の中で開発を進める必要があり、結果としてミッションクリティカルなシステム(業務の中核を担う重大なシステム)群の中に、他システムと密結合な状態で構築してしまいました。
その結果、
- システム停止リスクの影響が甚大で、機能追加が柔軟に行えない
- ポイント付与の色々なバリエーションを追加したくても、作業自体がリスクを伴うので新規施策が打ちにくい
- オンプレミス環境のためコンピューティングリソースはピーク時を想定して最大を確保せざるを得ない一方、平常時には過大な環境のため経済合理性に乏しい
- 運賃計算の誤りが許されない交通利用側の厳格なSLA(サービス品質保証)が、柔軟にテストマーケ等を行いたい物販利用でのポイント施策まで統制してしまう
といった多くの課題を抱えていました。
そこで今回話が挙がった「ICOCAポイント管理システム」刷新に合わせてモダナイゼーションしなければ、と考えました。どのように進めるべきか模索していたところ、当社の事業戦略遂行においてお世話になっているギックスさんからITアーキテクトである岡さんをご紹介いただいた、という経緯です。
岡さんとは最初に、現行システムの全体像を示した図をもとに意見交換を行い、色々なシステムが複雑に絡み合い、一つひとつ紐解くのも大変だ、という認識の共有からスタートしました。
その上で、「ではこのシステム群をどのように取り扱えばいいのか」という具体的な話をしていこうと思っていたのですが、岡さんから予想外な助言をいただきました。それは、案件の議論に入る前に「そもそも私たちが置かれている現状や行っていることは、世の中の流れから見たときにどういう立ち位置なのか」ということから問いを立てよう、という提案です。
最初は「なぜそこから議論を始める必要があるのか」と困惑しました。しかし、2006年,2007年頃を転機としてシステムを取り巻く環境が大きく変化してきたにも関わらず、我々はこの20年近く、時代の変化に取り残されているのではないか、新たなチャレンジをしていなかったのではないか、等と自問自答をするきっかけとなりました。
それを経た上で、これからの不確実な未来に向かっていくために、この「ICOCAポイント管理システム」改修プロジェクトをどう進めていくか、喧々諤々の議論を行いました。
その結果、従来のシステムの完成状態を定義しそれを前提として進めていく「クローズドエンド型」ではなく、「オープンエンド型・ロードマップ型」という、最初から完成形を決めず、段階的にチェックポイントを設けてモダンな姿に変化を遂げてく方式を採る判断をしました。
これは我々にとって大きな決断でした。当社は社会インフラ企業という立場上、ユーザーの要求に応えるためには「システムを止めないこと」が最優先、という考えでした。そのためには使い古された技術をベースとして、計画時点の要件を忠実に反映することが第一だという固定観念を持っていました。
しかしその結果、実はユーザーが持つもう一つの要求、つまり「柔軟かつ迅速なサービス改善」については、提供価値を失っていたことに気づきました。
そして、この2つの要求は現在の技術で両立可能であることを今回の岡さんから助言いただき、体現しようということになりました。
クラウド活用に必要な組織と人の変化
しかし我々は、モダナイズを進める上でクラウドリフトシフトすることが本質的にどういう意味を持つのか、十分に理解ができていませんでした。
岡さんに助言をいただく以前から、社内で「モダナイゼーションを進めよう」という掛け声のもと、パブリッククラウドの利用を前提にしたシステム構成の見積もりなどを各所と進めていました。しかし当時は我々のマインドセットが変わっていませんでしたので、従来のシステム構成やサービスレベルの担保に頑なにこだわってしまいました。結果、コストは上振れるけど、システムとして行うことが変わらない、というパブリッククラウドの良さを十分に発揮できない見積もりが出てきてしまい、元の木阿弥になっていました。
しかし、クラウドリフトシフトする理由の原点は「事業会社としての競争力を強化する」ことです。ですからオンプレミス環境と同じ思想でシステム構築を検討するのではなく、クラウドに適した、つまりクラウドネイティブな技術を採用し、最大限に発揮させたシステムの価値を、最終的にはステークホルダーに還元しなければいけません。そのためには技術だけでなく、組織も人も同時に変えなければいけない、ということを、今回のプロジェクトにあたって認識いたしました。
さらに岡さんから「組織や人の変化がないままクラウドへのシステム移管を計画することには、大きな落とし穴がある」との示唆をいただきました。
クラウドの大きな利点のひとつは「必要な時に、必要な分だけ、コンピューティングリソースを調達・返却できる柔軟性」であり、これによりコストの最適化につながります。
しかし従来のように、「万が一」を考慮し前もってリソースを厚めに確保しておこうとすると、本来不要な分までコストが著しく膨らんでしまうため、クラウドのメリットを活かしきることができません。
すなわち、”必要に応じて”オンデマンドでリソースを活用できるよう、システムを構成する各要素のサイズを小さく軽量に保っておき、何か変化が生じた際には改修も含めていつでも対応できる状態にしておく、という考え方が重要です。これにより、システムのアジリティ(機敏性)を確保する構成に見直すことが肝心だ、ということを岡さんに教えていただきました。
また、こうしたことはシステム部門だけが考えるのではなく、多くの関係者を巻き込むべき、という言葉も頂戴しました。
システムのオーナー、利用者、そして開発陣それぞれが、クラウドネイティブ技術の正しい理解を持ってシステムに適用することで、それぞれにとっての適切な便益が得られる――この考え方を軸、まさに“北極星”として据えながらプロジェクトを進めました。
その結果、刷新した姿を、以下に示しています。すべてのアーキテクチャを、これまで述べてきた思想に基づき検討してきました。
今回のプロジェクトを通じて、我々が過去から捨てられずにいた技術に縛られていたことが、企業としての競争力低下に繋がるリスクをはらんでいた、という教訓を得ました。
この状態から脱却するため、「より軽く、より早く」変化できる技術を適用し、その技術を使っていく中で、組織と人も共に成長していくことを目指しました。
“その先”を見据えたリアルタイムの顧客体験へ
今回「ICOCAポイント管理システム」のモダナイズにチャレンジし、我々プロジェクトメンバーは大きな手応えを感じました。
そこで、この熱量が失われないうちに、システム部門全体を対象とした勉強会を計5回にわたって開催しました。岡さんの考え方を根底から真髄まで共有し、システム部門のメンバー全員で取り組むことを旗印として掲げました。
そして、組織も人も変えていこうという機運が高まる中、今後のモダナイズ推進に向けたロードマップとして、次の3ステップで進めてまいります。
1つ目は、変化すべきシステムと不要なシステムをしっかり仕分けること。
2つ目は、システム更改は一括で行わず、「ロードマップ型」での段階的なアプローチを適用すること。
3つ目は、身についた自信や経験を基盤とし、組織と人の勢いを失わせないこと。
これらを着実に実行していくことで、自ずと道は拓けてくると考えています。
終わりにあたって、システムモダナイゼーションのその先を見据えた、当社グループの未来に向けた取り組みをご紹介します。
JR西日本グループでは「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」という「私たちの志」の実現に向け、様々なチャレンジを行っています。
その1つが、モダナイズによって刷新した各システムをリアルタイムで有機的につなぎ合わせ、お客様が“その瞬間瞬間に真に望むもの”を先回りしてさりげなくご提案できる仕組み――「リアルタイムリコメンド基盤」の構築です。
この取り組みは、ギックスさんが展開する顧客理解のためのデータ基盤活用サービス「CU/ADS(クアッズ)」を基盤にしています。お客様の行動や状況をリアルタイムに把握し、その瞬間に最適な情報や提案を迅速に届ける、という仕組みを今後も共に進化させてまいります。
最後に改めて、私たちの志「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」の実現に向け、私たちシステム部門も進化・成長を遂げていくことをここに誓いまして、本セッションを終了いたします。ありがとうございました。
【参考記事】
- 【前編】レガシー脱却から始まる、組織の意識改革と技術進化 JR西日本「ICOCAポイント管理システム」刷新がもたらした適応力の文化(2025.05.08)https://www.gixo.jp/blog/27306/
- 【後編】“顧客理解”を起点に、心地よい提案を届ける JR西日本 小山秀一氏が語る「CU/ADS」で叶えたデジタル時代の“おもてなし”体験(2025.05.08)https://www.gixo.jp/blog/27315/
f t p h l