「AI-Informed(AIインフォームド)」という行動様式 〜AIの力を借りて、人間がより良く決めるために〜|社長ブログ:ギックスが目指す世界
- TAG : AI | データインフォームド | 社長ブログ
- POSTED : 2025.07.03 16:15
f t p h l
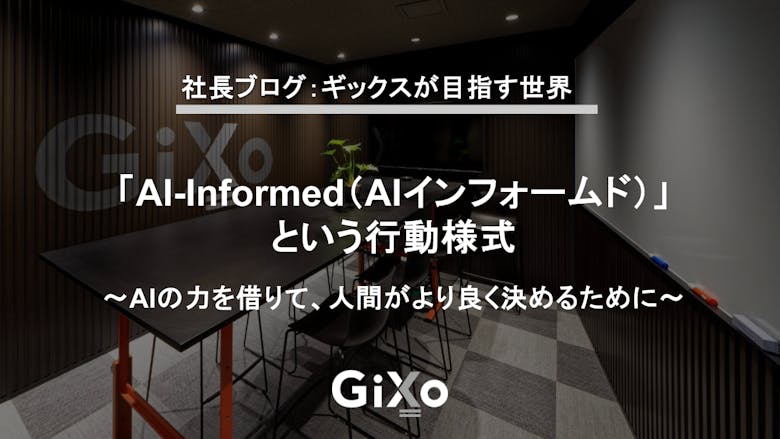
こんにちは。ギックス代表の網野です。
昨今、生成AIが社会に急速に広がっています。
もはや「ブーム」という言葉が正確ではないほどに、業務の中に“自然に組み込まれている”という印象を受けています。いわゆるアーリーアダプターを超えて、すでにレイトマジョリティ層にまで活用が広がっているのではないでしょうか。
今回は、当社のパーパス「あらゆる判断を、Data-Informedに。」と深く関連するキーワード「AI-Informed(AIインフォームド)」についてお話しします。
AIは何が得意で、何を任せるべきか?
AIの技術は急速に進化し、業務やサービスへの活用が日常になりつつあります。
とはいえ、「AIって何?」という問いに対して、シンプルに答えるのは意外と難しいものです。
ビジネスパーソンとしてざっくり捉えると、私はAIをこう定義しています。
AIとは、「人間のように、情報を理解し、考え、判断し、学ぶ力を持ったソフトウェアやシステム」です。
もう少し実務寄りに言えば、
- 人がこれまで“自分で考えていたこと”を代わりにやってくれる便利なツール
- 文章を書く、画像を生成する、予測する、パターンを見つける……そんな仕事をしてくれる存在
です。
ただし、注意すべきは「AIが正解を知っているわけではない」ということ。
あくまで「過去のデータから学んで、最もそれらしい答えを予測する」存在にすぎません。
だからこそ、今のビジネスに求められているのは、
この“最もそれらしい答えを予測する力”を、どの業務に、どう適用するか?
という目線なのです。AIを導入すること自体が目的ではなく、売上向上・コスト削減・判断の効率化にどれだけ寄与するかが勝負になります。
“人間の判断力”を拡張するAI。これがAI-Informedの本質
ギックスが掲げるパーパス「あらゆる判断を、Data-Informedに。」は、データ“も”使って、論理的に考え、より良い合理的な判断を人間が行う、そんな行動様式を意味します。
これは、勘・経験・度胸(KKD)だけに頼らず、かと言ってデータ“だけ”で物事を決めるのでもなく、データを有力な判断材料の一つとして使うという思想です。
その判断材料となるデータ(文章・画像・音声・グラフ・数値など)は、たとえ人間が徹夜で分析して導き出したものであれ、AIと呼ばれる仕組みによって自動で生成されたものであれ、“活用して判断する人間”にとっては出所より中身の有用性の方が重要です。
そして、その有用なデータを人間に“インフォームド=伝達”するまでの、
- 時間が短く、
- コストが安く、
- 判断にとって的確なかたちで
届けられるとしたら、それが一番良いと私は思っています。
今後、この“判断材料”はますますAIによって生み出されていくでしょう。
つまり、
AIが生成したデータや示唆をも、判断材料として受け取り、活用する。
それが「AI-Informed(AIインフォームド)」という考え方です。
最終的な判断を下すのは、あくまでも人間です。
ただ、その判断に使われる材料の中には、AIが出力した情報が当然含まれているという状態。
この状態こそが、私の考える「AI-Informedな判断」です。
「人間が判断する」理由は、思想ではなく経済合理性
「最終判断は人間が行うべきだ」というと、どこかヒューマニズムのような響きがあるかもしれません。
しかし、私の考えは少し違います。
現実には、
- デジタル化されていないデータ
- 定性的な状況
- 暗黙知
など、まだAIがうまく扱えない“曖昧さ”が世の中には多く存在します。
そうした領域で、「すべてのデータを取得する努力を行いAIに学習させるシステムを構築する」よりも、「人間が判断する」方が、今はまだ合理的なのです。
AIの進化における業務へのAI適用合戦が始まる
昨今、AIに関するニュースや議論で「機械学習」「アルゴリズム」「ルールベース」「生成AI」といった言葉が飛び交っています。
以下、あくまで個人的に考える実務ベースでの捉え方ですが、簡潔に整理してみます。
総称としてのAI:
「大量の過去データから学び、何かを判断・生成・予測してくれる」便利な道具
→ 一見“考えているように見える”システム群の総称。
ただし実際にはルールベースのものも、学習型のものも、“知能的に振る舞う”ものはビジネス界では広くAIと呼ばれていると思います。
機械学習(Machine Learning):
「過去のデータからパターンを学習し、予測や分類を行う技術」
→ 「データから学ぶ」という点がAIと呼ばれるゆえん。
商品レコメンド、需要予測、不正検知など、比較的ロジックが明快な意思決定に使われています。
アルゴリズム:
「あらかじめ設計されたルールに従って動く仕組み」
→ 決められた条件を処理するだけなので、学習はせず、狭義ではAIとは言われないと思います。
ExcelのIF関数や、閾値で振り分けるスクリプトなどが典型です。
ルールベース:
「人が定義した“条件と対処”の集合によって動作するシステム」
→知識をルールの形で人間が入力するが、複雑な判断も、ルールを組み合わせることで表現可能。
ルールベースはアルゴリズムを束ねた仕組みとも言え、狭義のAIとして呼ばれていると思います。
生成AI(Generative AI):
「入力に対して、文章・画像・音声など“新しく作る”アウトプットを返すAI」
→ 「最もそれらしい答え」を文脈から“予測して作る”ため、毎回違う返答になることも。
ChatGPTなどが代表例。従来のAIが「正解を当てる」ことを目的としていたのに対し、生成AIの本質は、「正解を求める」のではなく、「それらしい答えを“創る”こと」にあると私は整理しています。
このような強力なツールが使える時代に突入した今、すべての企業に問われているのは、
- 自社のどの業務プロセスにAIを適用するのか?
- どの判断をAIに任せ、どこに人間の意思を残すのか?
という、“業務適合性”に基づいたAI設計の視点です。
言い換えれば、「とりあえずAIを使う」から「どこに最も効果的に使うか」へと、問いが高度化しているということです。
これはかつて、BI(Business Intelligence)やアナリティクス、ビッグデータが企業に導入されていった黎明期の構図と本質的に変わりません。
あの頃と同じように、AIも“使うこと”が目的ではなく、“成果に結びつく業務適用”こそが価値を生むということを、今一度確認すべきタイミングだと思います。
つまり、どこにAIを使うのか、を“業務視点”で考える時代になったのです。
「どの業務に、どのテクノロジーを、どの粒度で適用していくのか?」
この問いを曖昧にしないことこそが、AI時代における組織変革と競争力の鍵になると、私は考えています。
AI-Informedの実践現場:整備士が判断を下すためのAI
ギックスでは、すでにAI-Informedの思想を現場に取り入れています。
たとえば、トヨタモビリティパーツ株式会社様と開発した「AI整備見積もりシステム」では、車両データや整備履歴から、AIが必要な部品交換を予測し、見積もり案を出力します。
そして、見積り案は一つの”インフォームドされるデータ”として用いつつ、最終判断を下すのは整備士の方です。
彼らはAIの示唆を踏まえたうえで、現場の状況や顧客との関係性を加味して、最適な整備プランを決定します。
このように、AIが作るデータを材料として活用することで、人間の判断はより合理的になり、サービスの均質化・信頼性向上にもつながります。
これはまさに、
「AIが出力した情報を活用して人間が判断する」=AI-Informedな業務判断
の一例です。
最後に:AI-Informedな組織とは?
AI-Informedという言葉は、単なるコンセプトではありません。
「AIの力をどう使い、人間がどう活かすか」という日々の思考習慣であり、そして行動様式です。
AIに仕事を“奪われる”のではなく、AIを使いこなして“質・量・スピード”を高めていく。
そんなチーム、そんな会社が、これからの時代の勝者になっていくと想定しています。
ギックスはこれからも、データインフォームドを根底に「AIと人間の共進化」を見据え、AI-Informedな行動様式を組織文化として根付かせていきたいと考えています。
そしてこの問いを、ぜひ皆様の組織にも投げかけたいと思います。
“私たちは、どの判断をAIに任せ、どの判断を人間で行うのか?”
f t p h l