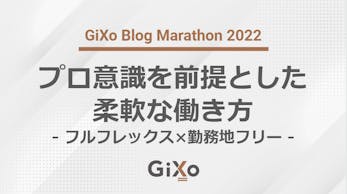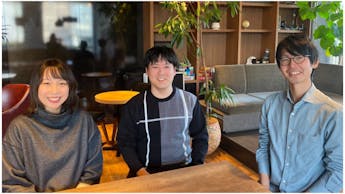プロジェクトのリードエンジニアとして、入社2年目ながら開発だけでなく、マネジメントや採用も担う釣谷 侑司。フルリモート・フルフレックスなど、ギックスならではの自由度の高い働き方と学べる環境を駆使して急成長を遂げた釣谷に、エンジニアとしてのキャリア形成や学習スタイルについて話を聞きました。
入社から2年半でエンジニアチームのリードを担うまでに成長
―まずギックスへの入社経緯を教えて下さい。
大学卒業後は地元の電力会社に就職し、火力発電所の運用保守業務を担当していました。コロナ禍でリモートワークが普及したことで、在宅勤務でデータ分析ができる仕事に就きたいと、転職を考えるようになりました。
‟データ分析”に興味をもったのは学生時代です。大学ではサービス業務を工学的に分析する「サービス工学」を専攻し、ある企業で、新人の客室乗務員を3年間でベテラン客室乗務員と同レベルのサービス水準に上げるための研究をしていました。
研究では、経験や勘など、習得に時間がかかることに対して、移動の導線などの取得可能なデータを集めて、実際の新人教育に活かす取り組みをしていました。この時、‟データを使って何ができるか‟を考えることに面白味を感じていたのです。新卒の就職のタイミングでは違う選択をしましたが、転職ではデータを扱う仕事をしたいという思いがあり、ギックスを選びました。

| 株式会社ギックス 釣谷 侑司 2017年東京大学工学系研究科精密工学専攻を卒業後、地元の電力株式会社に入社。火力発電所の運用保守を担当する。2022年9月にギックスに未経験エンジニアとして入社。データ基盤エンジニアとして、クライアントのデータ分析基盤構築プロジェクトに従事。その後、開発メンバーとして経験を積み、現在はデータ分析基盤構築プロジェクトにおいて開発チームのリードと管理をするとともに、社内エンジニアの育成・採用を担当。 |
―ギックス入社後はどのようなお仕事をされているのですか?
未経験エンジニアとして入社し、最初の3ヶ月はギックスのエンジニア研修プログラムを、その後の3ヶ月ほどは研修終了後に社内プロダクト改修のOJTを受けました。その後プロジェクトにアサインされ、開発に携わっています。
現在は、クライアントのデータ分析基盤の構築、改修などを担当しています。プロジェクトマネージャーの下で、5名体制のチームでのリーダーや、リードエンジニアとしてマネジメントも担っています。リーダーになってからは、メンバーとの1on1や、新しく入社された方のトレーニングも担当しています。
フルリモート・フルフレックスで働くエンジニアの1日のスケジュール

―1日のスケジュールについてお伺いしたいのですが、起床時間が非常に早いんですね。
ここ1年ぐらい、子どもの寝る時間に合わせて寝るようにしています。以前は子どもを寝かしつけた後に起きて勉強していたんですが、一緒に寝てしまったりと、安定して時間を確保できない状態でした。9時に寝て3時に起き、子供が起きるまでの時間を自分の時間にする方がリズムがとりやすかったので、このスタイルになりました。
ギックスはフルリモート・フルフレックスなので、もし子どもが熱を出したり、妻の体調が悪くなったりなど、家族の都合があれば柔軟に対応することができます。そして、それに左右されない朝の時間を学習時間として確保するようにしています。
私の場合は、新しいものを触るのが好きで、ただ本を読むだけでなく、手を動かしてトライ&エラーを繰り返すことで、できることが増えていくのが楽しい。それが継続できる理由かなと。
時間の取り方は人それぞれですが、ギックスのエンジニアメンバーは、自分でブログを書いたり、いろいろと触って実装してみたりと、実際に技術を試しながら学んでいるメンバーが多いですね。
―自己学習の必要性を感じたきっかけはあったのですか?
「こんなサービスが出ました」「アップデートがありました」など、世の中のいろいろな情報を目にしますが、それらを眺めているだけでは、エンジニアとしてプロジェクトで使える状況にないことがほとんどです。しかし、いつプロジェクトで使うかわからないし、使うとなった時にはスムーズに業務に取り込みたい。また、お客様から‟やってみたい”と言われた時に選択肢として出せるかは、日ごろから情報が追えているかどうか次第です。
自己学習は「幅」と「深さ」を意識して分けています。
「幅」は「情報収集の幅を広げること」で、技術書や技術ブログ、公式のリリースノートなどから幅広く新しい情報を得ることを目的としています。
「深さ」とは「深い知識やスキルを習得すること」。知識を深めるための学習として、きちんとした情報を取り入れ、実際にコードを書いて実装してみることを意識しています。ただ知っていることと、より深く理解しているとでは、実際のプロジェクトで課題に直面した際に適切な意思決定ができるかに違いが出てくるので、収集した情報を深掘る時間を確保することが重要だと思っています。
―スケジュールの10時にある「輪読会」は、釣谷さんが主催されていると伺っています。
輪読会は、業務に関連する知識を得るため、1冊の本を題材に内容について意見を交わす社内勉強会です。扱う書籍のジャンルは技術書から一般的なビジネス書まで多岐にわたります。週1回開催しており、参加者はエンジニアがメインの場合が多いですが、過去に『ライト、ついてますか ―問題発見の人間学』という問題発見に関する書籍を扱った際にはビジネスサイドの方やコーポレート部門の方も参加いただきました。ギックスは「業務の面倒ごとの解決への技術活用」に積極的な方が多いので、所属部門を問わず参加者は広く募るようにしていますね。
進め方としては、テーマとする対象を相談の上で決めて、その回の担当者が資料を作成して発表します。そして、発表した内容について参加者同士が議論をするというのがスタンダードな流れです。必ずしも資料を作成しなければならないわけではなく、全員が同じ本を読んできて、気になったところをメモして議論するなど、進め方は書籍によって柔軟に決めています。
| 【輪読会の基本の流れ】 • テーマとなる本や資料をチームで決定 • 各回の担当者が発表(資料作成は任意) • 気になったポイントをもとに議論 • プロジェクトへの活用も意識 |
輪読会の目的は2つあります。1つ目は、自分1人でやるより、人の意見を聞いた方が良い学びになり、自分の知識としてきちんと落とし込まれるということ。もう1つは、チームで開発を行っているので、それぞれの知識レベルが異なる場合、認識の齟齬が起きやすく、コミュニケーションが取りにくくなってしまうからです。みんなで議論することで、開発プロジェクトにおいてよりスムーズにコミュニケーションが取れるようになることを目的としています。
本を選ぶ際は、どれだけプロジェクトの業務に活かせるかを考えています。資料の作り方に関する本を題材にした時には、実際のプロジェクトで資料を作る時に‟こういう前提だったよね”と、スムーズに会話ができるようになります。エンジニアの原理原則を題材にした本だと、コードをレビューする際に、「読んだ本のようにして欲しい」など、共通言語ができるのでとてもやりやすくなりました。

―そのほかの業務についても教えて下さい。
リードエンジニアになってからはマネジメント業務が増えてきました。プロジェクトの人員調整やクライアントに説明するための資料作成、チーム内のタスク管理などの業務が4割ほどを占めています。残りの4割が開発、2割が採用を含めたその他の業務ですね。
定例ミーティングなどは午前・午後どちらかに寄せるように工夫しています。理由としては開発業務の効率化です。ミーティングの隙間時間で開発を行うとなると、効率が落ちてしまうため、定例に参加する開発メンバーは、できるだけミーティングの時間を寄せるように意識してスケジュールを立てています。
フルリモート・フルフレックスでも円滑なコミュニケーション
―みなさん自発的に学んでいらっしゃるという印象ですが、採用時にそのような方を採用していらっしゃるのですか?
そうですね。‟勉強している・勉強したい”という人はたくさんいらっしゃいますが、実際に手を動かしているか、自走できるかどうかというところを、採用面接で見るようにしています。
入社後の研修の作り方も意識していますね。「手順を細かく記載して、この順番でやってください」と教えるのではなく、「最終的にこういう形、こういう処理を行ってください」ということだけ伝えて、どう実現するのか、自分で考えるようなコンテンツの作り方をしています。
ギックスのエンジニアメンバーは、自ら「これをやってみて、こうだった」という情報を発信している人が多いです。「興味のあるセミナーを見つけたから行ってきていいですか?」と言われることもありますし、最近読んでいる本の内容を共有される方もいます。自分は技術書を出版するオライリー社のサブスクを会社として利用できるので、よく活用しています。ギックスには‟学びたい”という方が自ら学べる環境があると感じています。
―フルリモート・フルフレックスですので、普段のコミュニケーションはオンラインだと思いますが、何か意識していることなどありますか?
メインツールはSlackを使っていまして、基本即レスを心がけています。私以外のメンバーもみんなレスが早いですね。テキストコミュニケーションだけではなく、少し会話したい時などはハドル機能(短時間通話)で、気軽に声を掛けてもらうようにしています。話したい、と思ってから数分後には会話が始まるので、オフィス内の席で話しかけるのと、あまり変わらないスピード感だと思います。それでも話しかけづらいという人もいるはずなので、毎日最低でも15分は会話できる時間を設けています。
また、ギックスのSlackには、「times(タイムス)」と呼んでいる個人専用のチャンネルが全員分あります。何を書いても良いし、ギックスメンバー全員が他メンバーのtimesを読んだり投稿したりすることもできます。見つけた記事を貼ったり、こういうセミナーがあるよという情報を書いたりするほか、「こんなエラーで進まない」と書くと、社内のわかる人がクイックに教えてくれます。これはエンジニアだけではなく、ギックス全体の文化ですね。
| 【Slackチャンネル「times」の活用例】 • 「見つけた記事のシェア」や「気になるセミナーの共有」 • 「こんなエラーで困ってます…」→有識者が即レス • 雑談や近況報告も気軽に投稿 |
- フルリモートワーク制度をささえるギックス流コミュニケーションのいろは(2024/05/22)https://www.gixo.jp/blog/24568/
2年半でリードエンジニアに。成長も貢献も叶えられる環境
―ギックス入社後に感じたギャップや、成長を感じることはありますか?
入社前に期待していたことは、120%くらい叶えられています。いい意味でのギャップは、想像していたよりも成長が早いと感じているところですね。前職は5年勤めていましたが、‟この期間で何ができるようになったのか”と考え込むくらいですが、ギックスに入ってからは、2年半でリードエンジニアとしてマネジメントから採用まで任せてもらい、環境によって、ここまで速く成長できるのかと実感しています。今後の目標としては、技術力がありマネジメントもできるエンジニアリングマネージャーとしての力を伸ばしていきたいです。

ギックスの魅力は、自発的に動くことでスピーディーに学べる環境、同志・仲間が揃っているところです。ただ新しい技術が好きというより、目的は何か、クライアントにどう役立てるか、本質的な部分を考えられる人。目的を達成するために必要な技術を学ぶことができる人が求められていると思います。クライアントに貢献したい、自分も成長したいという方に向いていると思います。ぜひ、皆さんのご応募をお待ちしています!
- ギックスの採用情報はこちらhttps://hrmos.co/pages/gixo