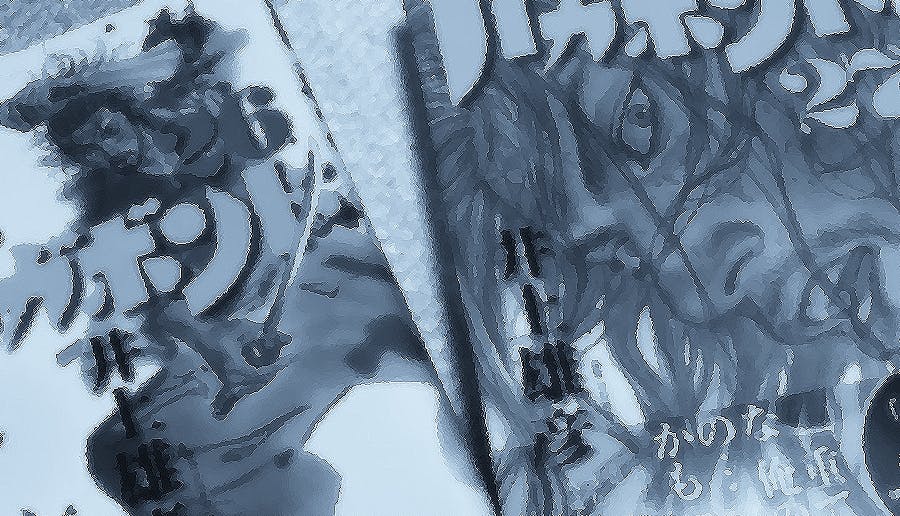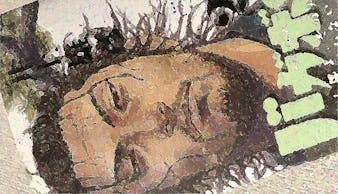目次
問いの設定を間違えてはいないか?
この連載では、バガボンドの主人公 宮本武蔵の”戦闘”シーンを抜き出し、武蔵の成長について読み解いていきます。前回、「第三十四戦(side:A)vs 吉岡一門 七十余名」では、武蔵の視点で読み解きましたが、今回は、side B として、吉岡の当主、植田の視点で読み解きます。
連載の概要はコチラから。
「使えないコンサル」と同じ失敗
僕は、前々回(第三十三戦)、植田の冷静な観察眼に基づく合理的判断について考察しました。そして、その結果がどうなったのかは、前回(第三十四戦:Side A/武蔵視点)既に述べた通り「壊滅」です。
なぜ、圧倒的有利を誰もが疑わぬ 70 対 1 の戦いが、そのような惨敗に終わったのでしょうか。僕は、この失敗は「コンサルの使いどころの失敗例」と酷似していると思うのです。本日の 第三十四戦:Side B/吉岡一門視点 では、そのあたりに着目して読み解いていくことにしましょう。
実現性(Feasibility)チェックと実行計画
今回の植田の判断は、合理性という観点では非常に優れた判断です。この戦いは「普通に考えたら勝てる」戦いです。従って、吉岡一門には戦いを回避する理由はありません。
- 70対1で戦いを挑み、やってきたら大勢で襲い掛かって殺す。その後、「正々堂々と戦って、仇討ちした」と言いふらす。
- もし、武蔵がやってこなかったら、逃げた、と言いふらす。
の二択です。むしろ、この選択肢を選ばない場合は
- 先々代当主 吉岡清十郎(兄)、先代当主 吉岡伝七郎(弟)を殺されたのに、仇討ちもしない臆病者集団 という噂がたつ
ということになります(というか、既に、吉岡恐れるに足らず、という輩も出始めています)ので、戦うしかない、と言うべきかもしれません。従って、聡明なる新当主 植田が「武蔵を迎え撃つべく、一条寺下がり松にて70余名で陣取る」という選択をしたのは、至極当然の判断です。
しかし、「普通に考えたら勝てる戦」であるがゆえに、大変残念なことに「実現性(フィージビリティ)」の観点でのチェックが甘く、また、「実行計画」の策定において緻密さを欠いていました。
実現性の肝は”要素分解”
実現性(フィージビリティ)とは、その計画・企画が、実際に実行することができるか・実現に至る可能性(正確には蓋然性、ですが)が高いかどうか、を意味します。
今回の事例に関して、実現性の観点で要素分解すると・・・
- 武蔵が現れるかどうか →五分五分。但し、来なかった場合は不戦勝扱いになるので、失敗リスクなし。
- 武蔵を70人で迎え撃つ →吉岡門下生は全員参加するので、失敗リスクは極めて低い。
- 70人総がかりで武蔵を殺す →武蔵がいくら強いとはいえ、70人を倒すなんてありえない。失敗リスクは極めて低い。
- 悪い噂が立たないか →早朝に人通りが無い一条寺下がり松で行うため、人には見られない。吉岡門下生の口裏合わせは万全。
という感じでしょうかね。このように考えると、明らかに実現性が高そうだ、と思います。
実行計画に落とすと”無理”が見える。
しかし、実現性チェックの際に考えた各要素を、本当に実行しようとすると、幾つかの点で困難性があることに気づきます。植田は、この観点での確認を怠り、対策を練り損ねたと言えます。
特に難しいのは、「70人総がかりで武蔵を殺す」というポイントです。
例えば、”一斉にとびかかって殺す”というのは、道場で 1 vs 1 の訓練しかしていないメンバー、戦場での実戦経験がないメンバーにとっては「どうやっていいのかわからない」でしょう。具体的には、どのタイミングで、どの方向から斬りかかったら良いかが分からない、のです。この部分は、十剣の一人、余一が解決策を導き出しました。余一曰はく「あれほどの男が相手 一対一を順番に七十回やるような戦い方はうまくない 一番いいのは『一斉にグチャグチャに』だ」となります。
あるいは、”味方を傷つけてでも武蔵を殺す”というのはどうでしょう?日々、共に研鑽を積んだ仲間です。同じ釜の飯を食った仲間です。それを「目的(=武蔵を殺す)達成のために、大事な仲間を自らの刃で怪我をさせて良い。場合によっては、その命を奪っても良い」というのは、実行するかどうかの前に、頭で理解することさえも困難でしょう。実際、余一が、余一塾のメンバー(7名)と「一斉にとびかかってグチャグチャにする」と決めたにもかかわらず、余一塾生は、決死の覚悟で余一が押し倒した武蔵を、余一もろとも突き刺す、ということが全くできませんでした。結果、余一は無駄死にすることになります。
そもそも、”殺す”という行為そのものが、大半のメンバーにとってはハードルが高いはずです。時代は江戸時代、天下太平の世です。剣術は、己を磨き上げる自己研鑽の道具となりました。自らの手で人を殺した経験があるメンバーも少ないでしょうし、真剣で誰かを斬った経験があるかどうかも怪しいものです。まったく切れない粗悪な刀しか携えていない者、腰が引けてしまう者、命のやり取りをする覚悟ができていない者、そういう門下生が沢山いたために、全体としての品質は低下してしまっていたと言えます。
役割分担の明確化が鍵だったはず
あるいは、「武蔵を70人で迎え撃つ」というのも、簡単ではありませんでした。今回、昨夜の宿泊場所からまっすぐ一本道を向ってくるという想定で陣を構えていた吉岡一門に対し、後ろの山から現れた武蔵は、戦いの前の陣地の全容を見渡し、おそらく、どこに総大将たる植田がいるかの目星もつけていたと考えられます。その結果、70余名という軍勢の中に分け入って、なんと”3番目”の相手として植田を見出し、刀を抜く暇さえ与えずに、片耳ごと顔の側面を削ぎ落す大怪我を与えます。
武蔵襲撃の際、植田の付近にいた一人の門下生は、先輩格に対して「まだ半刻(つまり1時間)ほどあるので、この間に、武蔵と最初に相対する正面口のものと後退してきて良いか」とたずねています。
吉岡清十郎の言葉を借りるなら、「処女(おとめ)のように暢気(のんき)だな」となるでしょう。(参考記事:第三十二戦 vs吉岡伝七郎”決着” )どういうことか?それは
- 武蔵は定刻通りにやってくる
- 武蔵は正面からやってくる
- 自分のところには順番は回ってこない(から、手柄は立てられない)
という甘い考えに侵されているということです。
本書内の描写では、武蔵が意図的に定刻より早く来たわけでも、裏側からの奇襲を計画していたわけでもない、と言う風に表現されています。しかし、70 vs 1 という圧倒的不利な状況で、相手が正面突破をすると無邪気に信じているのは、おめでたいとしか言いようがありません。
つまり、植田の周りに配置されたメンバーは、「定刻前から、常に周囲に気を配り、武蔵が奇襲をかけてこないか見張る」「もし武蔵が現れたら、大声で周囲に知らせて体制を整える」ということを最優先に置くべきだったわけです。もし、この門下生が武蔵襲来に気づいて大声で知らせていれば、少なくとも、植田が刀を抜く間もなく斬られることはなかったでしょう。しかし、門下生は、武蔵に斬りかかり、一刀のもとに切り伏せられてしまいます。
彼は、彼に課せられた責務を果たせなかった、というか、そもそも、理解していなかったと言えます。
勝利条件の周知徹底が足りない
このようなことになったのは、結局のところ指揮官もしくは作戦立案者の「想像力の欠如」に起因します。また、「オペレーションへの落とし込み不足」も大きいですね。
吉岡一門にとって、この戦いの勝利条件は ①武蔵の殺害 ②植田の生存 でした。しかし、先ほどの門下生にとっての勝利条件は「自分が功名をあげること」「次世代の十剣の一翼となること」だったわけです。この乖離は大きいですね。
つまり、吉岡一門の敗因を端的に述べるなら、メンバーのベクトルを揃えられなかったこと、と言って良いでしょう。完全なる指揮官のミスです。
自分事(じぶんごと)になると目が曇る
僕は、植田良平という男は、非常に聡明で冷静な漢だと思います。現代であれば、コンサルタントになることもできるでしょう。そんな彼が最も輝くのは、やはり「道場の経営参謀」として、実務を取りまとめるポジションだったのではないかと思います。いわゆるCOOです。
しかしながら、彼は、今回、当主に選ばれます。誰も反対しません。適材だと考えていたのでしょう。しかし、残念ながら、彼は神輿を担ぐ天才であって、神輿に乗るタイプの天才ではなかったのです。
もし、伝七郎が大将として座っていたら、植田は参謀として以下のような行動をとったでしょう。
- 大将の周りに十剣を2名ほど配置する
- 大将の背後にも、10名程度の後備えを配備し、万が一武蔵が現れた場合の対処法(大声をあげる。それも、自分に割り当てられた数字を叫ぶことで、正確な場所を伝えられるようにする くらいのことは考えそうですね)を設計し、徹底させる
- 武蔵が正面に現れた際には、後備えを解除して、大将の全面防御に再配置する
- 自らは、伝七郎の傍で戦況を見守り、指揮を執りつつ、最後の備えとして、いざとなれば自分の身を挺してでも大将を守る
これくらいのことは、参謀としての植田ならできて然るべきです。なぜなら「守るべきは当主の命」だということが明確にセットされ、自分の命も捨て駒として使う覚悟があるからですね。
しかし、今回、「守るべき当主の命」は「自分の命」です。これは、おそらく、植田にとっては実感を伴わなかったことでしょう。植田にとっては、当主は、今もなお「伝七郎」です。そして、伝七郎亡き今、植田が守ろうとしているのは、「吉岡一門というブランド」です。
結果的に、勝利条件は不明瞭になり、打つべき備えも打てず、実行計画もおろそかになり、作戦は周知徹底されませんでした。いや、これ、ほんとに戦略失敗のあるあるですよ。期末試験に出るんで覚えておきましょうレベル。
ここまで読んでいただいた皆様にはお分かりいただけていると思うのですが、植田の失敗は、合理的に考えすぎたということではなく、戦略上の目的が曖昧なまま前に進んでしまった、ことにあります。彼が守りたいのが「吉岡一門というブランド」であれば、他の十剣の「植田の命を守れ」というマインドを修正する必要があります。あるいは、他の十剣と話した結果「植田の命=吉岡一門というブランド」と言う風に、植田自身が納得するということでも良かったでしょう。このステップを飛ばしてしまったことが、吉岡一門の壊滅・破滅を招いたわけです。
こういう話、おそらく、植田が、十剣と伝七郎との間で同様のやり取りが為されているのを横で見ていれば、簡単に気づいたはずなんです。こういうところが「コンサルのいる意味とは何か?」(関連記事:経営コンサルタントと戦略コンサルタントの違い)であったり、「コンサルが経営者として大成するかどうか」(関連記事:起業家は「無から有」、コンサルは「有から優」。)という議論に直結する話なわけです。
やっぱ、自分事を、100%の客観性をもって判断するのは難しいです。コンサルタントという”客観性の塊”をうまく使いこなすことで、経営者は自身の「論理性」「合理性」そして「熱い思い」を効率的に実行することができるのだと僕は思います。
1年という時間を、活かせたか?
最後の最後、「一(ひとつ)の太刀」を武蔵の背後から降り降ろし、その右足のふくらはぎに剣士生命を脅かす大きな傷を与えたとき、植田の頭に去来したのは、師 吉岡拳法の言葉でした。
一(ひとつ)の太刀(たち)
いま!! ここ!!
「次」はないっ!!
道場の経営参謀としての重責を背負い、清十郎・伝七郎兄弟が亡くなった後は、悲しみを押し殺して、気丈に当主として振る舞ってきた彼が、最後の最後、剣士に戻れたのは幸せだったと言えるかもしれません。
思えば(劇中の)一年前、武蔵の道場破りの直後、焼け落ちた道場を片付けながら、植田良平はこう言いました。
試練は何のために与えられると思う もっと強く大きくなるためだろう (バガボンド 第4巻)
彼は、この時、未来を向いていました。しかし、伝七郎を失った時、植田の時計は止まり、彼は過去を向いて進むことになったのです。名声をとどろかすのではなく、汚名をそそぐことに重きを置きました。道場を拡大するのではなく、評判を守ることに目を向けました。
1年間という時間が、武蔵に与えた成長を受け止めるには、吉岡道場は硬直化しすぎていたのかもしれません。スタートアップと、大企業の構図にも似ていますね。
この、読み解きを始めた当初(2015年12月)、僕は、こんなことを書いています。
清十郎の懸念の通り、1年後に京都に舞い戻った武蔵は、吉岡伝七郎どころか、その兄である吉岡一門当主 清十郎さえも圧倒する強さを身につけています。 武蔵が最初に吉岡伝七郎と勝負をしたとき、彼は、17歳で宮本村を離れてから4年間の武者修行をした後のことでした。僕たちも3年をかけて、なんとか吉岡道場に殴り込もうと思える程度には成長したと思っています。(コテンパンにやられちゃうおそれは多分にありますが。)ただし、今から1年後の2016年12月12日に、吉岡一門を打ち破れるほどの成長を僕たちが遂げようとすると、こんな成長速度では間に合いません。
結局、劇中の1年間を読み解くのに、現実世界の2年間を費やしてしまいましたけれど、僕たちは、どの程度の高みに上れたのだろうか、と自問すると、なかなか恥ずかしい気持ちになりますね。1.01の365乗は、37.8倍。それが2年なので、1,428.8倍。それを目指していたハズですが・・・
この週末、バガボンドと読み解き連載を読み直し、弊社(ギックス)の成長に加えて、自分自身の成長がいかほどのものかを見つめなおしてみたいと思います。
連載の全体像はコチラから。